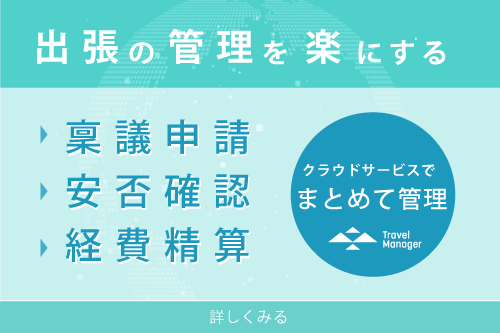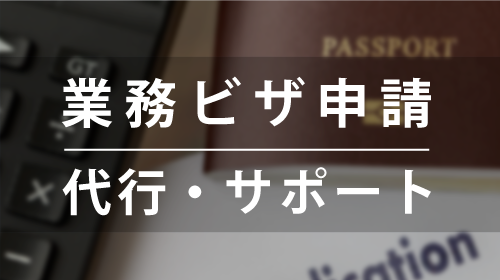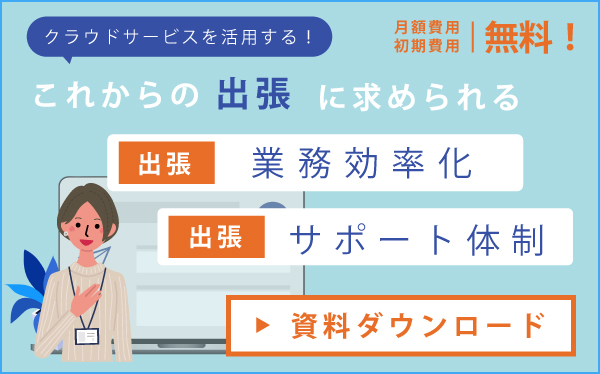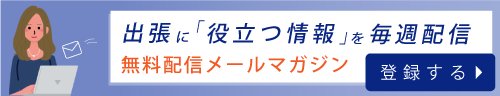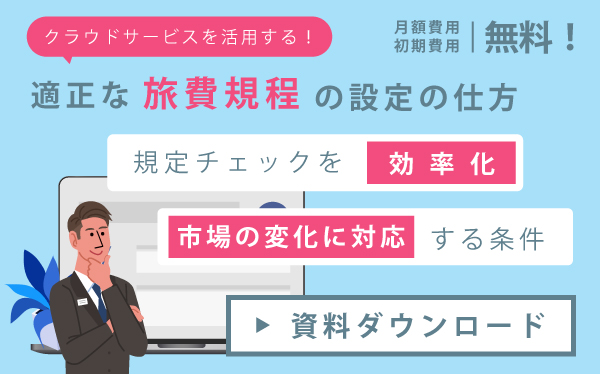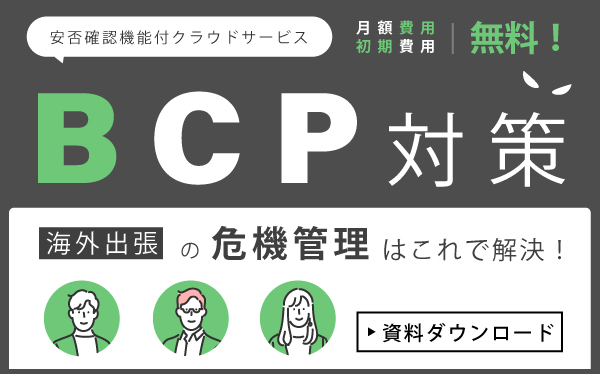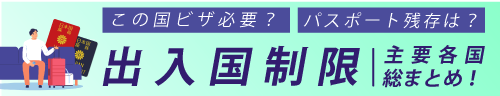日本版ESTA「JESTA」とは?
公表された制度構想をわかりやすく整理
2025年4月以降、政府はJESTA(日本版ESTA)と呼ばれる新たな電子渡航認証制度の導入に向けた構想を段階的に公表しています。
制度の名称は「JESTA(ジェスタ)」。米国のESTA、韓国のK-ETA、カナダのeTAなどと同様に、テロ対策や不法滞在の防止、入国審査の効率化を目的とした、いわゆる「事前入国審査」の仕組みです。
現時点では、JESTAはあくまで制度化に向けた検討段階にあり、詳細な運用ルールや導入時期は今後固められていく見通しです。
本記事では、2025年7月時点で公表されている政府発表や報道内容をもとに、構想の全体像や導入の背景、今後注視すべきポイントを整理してご紹介します。

目次
JESTAとは何か ─ 日本版ESTA構想の概要

電子渡航認証制度とは
電子渡航認証制度とは、ビザ(査証)が免除されている国・地域からの渡航者に対し、渡航前にオンラインで申請・審査を行う仕組みです。米国の「ESTA」や韓国の「K-ETA」、カナダの「eTA」などが広く知られており、不法滞在やテロリスクの抑制、入国審査の効率化を目的として導入されてきました。
こうした制度では、渡航者が出発前に自身の個人情報や渡航目的などを専用フォームで申告し、各国の入国管理当局がその情報をもとに、渡航許可を出すかどうかを審査します。認証がない場合は航空機への搭乗そのものが制限されるのが一般的です。
「JESTA」という制度名の意味と由来
日本においても、こうした電子渡航認証制度の導入に向けた検討が進められており、その構想に付けられた名称が「JESTA(ジェスタ)」です。
これは「Japan Electronic System for Travel Authorization」の頭文字をとったもので、日本版ESTAと位置づけられています。
法務省や出入国在留管理庁によると、2025年春に制度の概要が一部発表され、名称も正式に「JESTA」と決定されました。現時点ではまだ制度として確定したわけではなく、導入に向けた制度設計とシステム開発が進行中です。
公表された対象者と適用範囲
JESTAの制度案によると、短期滞在ビザが免除されている71の国・地域からの渡航者が対象とされています。観光、ビジネス、会議出席、短期出張などを目的とした入国がこれに該当します。
申請時には、氏名・パスポート番号・滞在目的・宿泊先などの情報が求められ、政府による事前審査を経て「認証」が与えられます。審査に問題があると判断された場合は認証が下りず、航空機への搭乗もできない仕組みが想定されています。
このように、JESTAは出入国審査を事前化・電子化することで、水際対策の強化と入国管理の効率化を両立させることを目的とした制度構想です。
制度導入が検討される背景と政策的な意図

不法滞在やテロリスクへの対処
JESTA構想が打ち出された背景には、不法滞在者の増加や潜在的な治安リスクへの対応強化があります。
2024年1月時点で日本国内の不法滞在者数は約7万5千人にのぼり、そのうち約2万8千人が短期滞在ビザ免除国からの入国者であることが明らかにされています。中には、観光などを名目に入国し、在留資格を超えて滞在し続けるケースも含まれています。
こうした現状を受け、政府は「不法滞在者ゼロプラン」を打ち出しており、JESTAもその一環として位置づけられています。
制度が導入されれば、事前段階での情報審査が可能となり、ハイリスクな渡航者を選別できるようになるため、水際での対応力が高まるとされています。
訪日外国人数の増加と審査業務の負担
一方で、日本を訪れる外国人の数も年々増加傾向にあります。政府は2030年に訪日外国人年間6,000万人の受け入れを目標に掲げており、入国審査の現場では対応業務の増大と混雑が課題となっています。
現在の「Visit Japan
Web」などの仕組みでは、出発後の情報提出や現地での審査が基本ですが、JESTAが導入されれば事前確認済みの渡航者はスムーズに自動ゲート通過が可能になるなど、現場負担の軽減も見込まれています。
出入国在留管理の「厳格化と迅速化」
法務省・出入国在留管理庁は、JESTAを「厳格な管理と審査スピードの両立」を実現する制度と位置づけています。
これは、国会・閣議後の発言でも繰り返し強調されており、JESTAの意義として次の2点が明確に打ち出されています。
・選別力の強化(入国可否を事前に判断)
・審査の効率化(システム化による負荷軽減)
つまり、JESTAは単なる認証制度というだけでなく、出入国行政全体のデジタル化・高度化を進めるための一手として位置づけられていると言えるでしょう。
検討されている制度の仕組みと想定される流れ

想定される申請情報と手続きの流れ
JESTA構想では、渡航前に申請者本人がオンラインで情報を登録し、政府の審査を経て「認証」を受ける仕組みが想定されています。 公表された情報によれば、入力項目は以下のような基本情報です。
氏名、性別、生年月日 パスポート番号・有効期限 渡航目的(観光、商用、短期出張など) 滞在予定地・宿泊先 職業や連絡先情報 など
申請内容は出入国在留管理庁が審査し、リスクが低いと判断された渡航者に「認証」を発行します。この認証を取得していない場合、航空機や船への搭乗自体が拒否されることになります。
認証取得が渡航の前提となる仕組み
JESTAの認証は、入国審査における事前スクリーニングの役割を果たすものです。
制度が導入されれば、認証を受けた渡航者は、入国時の審査をスムーズに通過できる可能性が高くなります。
現在、入国審査は現地空港で行われるのが主流ですが、JESTAによって一部の審査プロセスが「出発前」に移行することになります。これにより、入国時の審査待ち時間の短縮や、審査官の負担軽減も期待されています。
現行のVisit Japan Webとの違い
現在日本が運用している「Visit Japan
Web」は、税関・検疫・入国審査などの各種手続きを一元化するための事前登録システムですが、これは「事前手続きの利便化」を目的とした仕組みです。
一方でJESTAは、入国の可否そのものを事前に判断する「審査制度」して構想されています。つまり、Visit Japan
Webは任意登録による効率化ツール、JESTAは原則必須となる認証制度として役割が異なります。
そのため、JESTAが正式に制度化されれば、Visit Japan Webとの併用や統合も含めた制度再編の可能性も今後検討課題になると考えられます。
入国管理との関係 ─ 不法滞在・難民審査との接点

不法滞在者ゼロプランとの連動
JESTAは、単なる渡航手続きの電子化にとどまらず、出入国在留管理の厳格化と連動した施策として位置づけられています。
2025年5月、法務省は「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」を発表し、JESTAをその一環と明言しました。
特に焦点が当てられているのは、ビザ免除国からの短期滞在者の不法残留です。政府発表によると、不法滞在中の外国人のうち約6割がビザ免除国からの渡航者であり、水際での選別強化が急務となっています。
JESTAにより、こうしたリスクのある渡航者を出発前の段階で把握・排除できる仕組みが構築されると期待されています。
難民申請制度における審査の迅速化
JESTA構想と並行して、政府は難民認定制度の見直しにも取り組んでいます。
特に、明らかに難民に該当しないと判断される申請(いわゆる「B案件」)については、新たな分類手法によって迅速に処理し、在留資格の付与を避ける運用が始まっています。
JESTAが導入されれば、難民認定とは別の枠組みであっても、出入国審査の段階で疑義のある渡航者を早期に排除する仕組みが加わることになります。
結果として、難民審査への誤用・濫用的な申請の抑止効果も期待されているといえるでしょう。
JESTAが果たす「水際対策」の役割
JESTAは、いわば“搭乗前の審査”によるリスクブロック機能を担います。
現在、日本への入国を拒否するためには、原則として入国空港での対応が最終的な判断点となりますが、JESTAによってその判断をより前段階(=渡航準備段階)で可能にするのが大きな特徴です。
このように、JESTAは単なる技術的な仕組みではなく、不法滞在・難民制度・送還体制といった広範な入国管理政策と密接に関係する制度として検討が進められていることが分かります。
他国の電子認証制度との比較とJESTAの位置づけ

ESTA(米国)、K-ETA(韓国)、eTA(カナダ)の概要
日本が導入を検討しているJESTAは、すでに複数の国で運用されている電子渡航認証制度を参考にした構想です。代表的な先行例は以下の通りです。
| 国名 | 制度名 | 有効期間 | 申請費用 |
|---|---|---|---|
| 米国 | ESTA | 2年間 | 21米ドル |
| 韓国 | K-ETA | 2年間 | 10,300ウォン※ |
| カナダ | eTA | 5年間 | 7カナダドル |
※K-ETA制度自体は現在も韓国で継続運用されており、日本など一部の国に対しては観光促進のため一時的に適用が免除されています。
いずれの制度も、ビザ免除国の渡航者に対して、入国前にオンラインでの事前認証を義務付ける仕組みであり、セキュリティ対策と入国審査の効率化を同時に実現することを目的としています。
JESTAとの共通点と相違点
JESTA構想は、これらの制度と多くの点で共通しています。具体的には、以下のような仕組みが検討されています。
・オンラインでの個人情報・渡航目的等の申請
・渡航前の審査によるリスク判断
・認証の有無によって搭乗可否が決まる
一方で、JESTAはまだ制度設計の途中であるため、有効期間や申請手数料、対象国の範囲などは未定です。また、法制度上の位置づけや他のシステム(例:Visit Japan
Web)との統合可能性も含め、制度の柔軟性が検討されている段階にあります。
国際標準に向けた日本の制度整備
出入国審査に関する国際的な潮流を見ると、「事前登録による安全確保と業務効率化」は各国で共通の課題となっており、電子渡航認証制度はその解決策として定着しつつあります。
JESTAもこの文脈の中で、日本が国際標準に合わせて出入国制度を近代化するための取り組みの一環と位置づけることができます。
特に、2028年度中の導入を目標とする前倒し方針が示されたことは、制度化への動きが政策的にも優先度の高いものであることを示しています。
今後の検討スケジュールと注視すべきポイント

2028年度中の導入目標と今後の工程
JESTAについては、当初2030年頃の導入が想定されていましたが、2025年春の国会答弁において、導入目標が2028年度中に前倒しされたことが明らかにされました。
システム開発や法整備の加速を図りつつ、必要な審査体制の整備を進めることが前提とされています。
現時点では、制度の詳細や申請手続き、運用開始時期などは確定しておらず、検討中の段階にあります。
法制度の整備、予算措置、民間事業者との連携なども含め、今後数年にわたって段階的に情報が公表されていく見通しです。
制度化に向けた論点と未確定事項
JESTAが制度化されるにあたり、次のような論点が残されています:
認証の有効期間や更新の仕組み 申請手数料の有無と金額 Visit Japan Webとの統合・併用の可否 認証取得の義務化対象(全渡航者か、一定条件のみか) 航空会社・旅行会社など民間側の対応負担
これらは、制度運用の現実性と渡航者・関係事業者双方の負担とのバランスを取る上でも、今後の議論の焦点になると見られています。
企業・渡航者としての情報収集の重要性
制度がまだ構想段階であるとはいえ、将来的にJESTAが「渡航の前提条件の一部」として位置づけられる可能性があり、外国人顧客やパートナーを受け入れる機会の多い日本国内の企業にとっても、制度の動向を把握しておくことが重要です。
現時点での対応は不要ですが、今後の制度化に備えて、
・法務省や出入国在留管理庁の公式情報を定期的に確認する
・ビザ免除国との関係性を再確認しておく
・新制度によるスケジュール影響(認証取得のタイムラグ)への理解を深める
といった情報リテラシーが求められてくるでしょう。
まとめ
JESTA(日本版ESTA)は、短期滞在ビザ免除国からの渡航者に対し、渡航前にオンラインで認証を取得することを求める制度構想です。
不法滞在やテロリスクの事前抑止、入国審査の効率化といった複数の政策目的を背景に、2028年度中の制度導入を目指して政府による検討が進められています。
現時点では、申請の詳細や運用開始時期などは未定であり、JESTAはあくまで制度案の段階にあります。ただし、米国や韓国などで既に運用されている電子渡航認証制度を参考にしていることから、一定の制度的枠組みが想定されている点は注目に値します。
今後、法務省や出入国在留管理庁などから制度設計に関する情報が順次発表されていくと見られるため、関係者にとっては制度の進展状況を継続的に確認していくことが求められます。
訪日渡航の前提条件が将来的に変わる可能性がある以上、企業や団体の立場でも制度の仕組みと背景を正しく理解し、必要なタイミングで柔軟に対応できる体制を整えておくことが望まれます。
- 初期費用と使用料が「無料」
- 出張者が個々に予約、費用は後払い一括請求
- 手配先の統一と出張データ(費用)の管理
- 24時間365日出張者をサポート
- チャット機能でメッセージの送受信